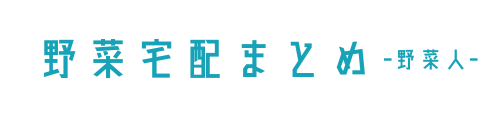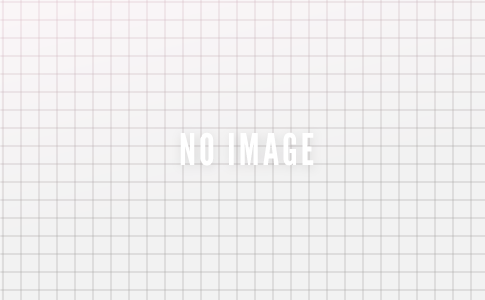私は、アグリメディアが運営しているシェア畑という、畑をレンタルして家庭菜園を楽しむサービスの会員ですが、先日、そのシェア畑の講師の方が定期的に実施している無料の有機野菜づくり講座を受講してきました!
シェア畑とは?についての詳しい情報や私の体験談は別途記事で掲載しています↓
・見学・入会体験談:中浦和のシェア畑を始めました!
・【特徴や料金】シェア畑のメリット・デメリットを評価してみた!
私はシェア畑に入会してまだわずかであり、実際に畑で作業するのはこれから。
シェア畑で作る野菜は全て有機野菜ですが、有機野菜は一般の野菜より育てるのが難しく、正しく栽培するには特殊な技術や専門知識が必要とのことで、何も知らない私は、大丈夫かな・・・ちゃんと育てられるかな・・・と不安に感じていたところ!
メーリスで、シェア畑を本格的に始める前に有機野菜づくりについて座学の講座で学びませんか?というお誘いを受け、これだこれだ!と思わず飛びついてしまいました^^
参加費は無料で、開催日時や場所もマッチしたので、なおよし☆
本講義では、下記のような内容を学びました:
・有機野菜とは?一般野菜との違い(見た目、美味しさ、栄養価)
・有機野菜はどのように作るの?農薬や肥料について
・有機野菜と一般野菜の安全性の違いは?スーパーの野菜を使った「エグミ」成分の実験的な測定をもとに徹底解説
・なぜ海外では有機野菜が浸透するのか?日本人と外国人のオーガニックに関する意識と関心の差
・有機栽培を詳しく学ぶための学校「アグリアカデミア」の紹介
などなど。
私は、もともと、シェア畑以外にも、有機野菜の宅配サービスを複数社利用しており、有機野菜についてネットでいろいろと調べることは何度もしていましたが、今回受けたセミナーの知識はなかなか書籍やネットサーフィンを通じては得られないような貴重な情報でとても満足しました。
今回は、有機野菜にちょっと興味がある方や、これから有機野菜づくりに挑戦してみたいという方向けに、講義内容や私の感想をご紹介します!
目次
- 有機野菜と一般野菜の違いについて
- 硝酸(野菜のえぐみ成分)を測る実験
- なぜ日本人と外国人は有機野菜に対する関心・意識が違うのか?
- 有機栽培、自然栽培、無農薬栽培の違いは?
- 有機野菜作りの学校「アグリアカデミア」の紹介
有機野菜と一般野菜の違いについて
今回の講座を担当してくれるのは、農業NPOとシェア畑の社員である三平さんという方。
私は東京農業大学を卒業後、現在、茨城で農業NPOに勤務しながら、シェア畑の準社員として有機野菜栽培の研究に携わっています。
今日はお越しいただきありがとうございます。
よろしくお願いします!
よろしくお願いします^^
有機野菜は日本全校で何%くらいだと思いますか?
ん〜・・・10%?20%くらい?だいたい、1/5くらいのイメージです!
99%が農薬や化学肥料を使っている慣行栽培です。
へ〜!そんなに少ないのですね!確かに、一般スーパーでは有機野菜コーナーはほとんど見ないですしね・・・
しかし、なぜそんなに少ないんだろう・・・?
特にアメリカと欧米では、有機野菜の畑が多く、一般的な栽培から有機栽培への積極的な転換が行われています。
ではなぜ海外では有機野菜がここまで広まっているのに日本ではまだまだなのか?
こちらについては、有機野菜の作り方のパートをお聞きすればわかってくるので、最後にお伝えします。
楽しみにしていてくださいね!
ん〜・・・気になる!けど、まずはおとなしく講義全体を聞きましょう^^;
まずは、こちらの小松菜の2つの写真を見てみてください。
スーパーに行ったとしたら、どっちの小松菜を買いたいと思いますか?

ん〜・・・右のほうが葉っぱがシャキッしていて色も綺麗。右のものですかね・・・
左は、見た目があまりよくないですよね。
淡い色で元気がなさそうです。
味も、あまり美味しくなさそうな印象ですよね。
しかし、実際のところ、2つ食べ比べてみると、左の有機野菜のほうがえぐみが弱く、味や食感が美味しいのです。
確かに、有機野菜は形があまり綺麗じゃなかったり、虫食いがあるイメージ!
有機野菜は、見た目だとあまり美味しく感じず、逆に農薬と化学肥料を使って作った野菜のほうが色鮮やかで美味しそうに一見見えます。
では、そもそもなぜこのような見た目の違いが出てきてしまうのか?
それは、有機野菜の栽培方法に深く関係しています。
有機栽培と慣行栽培の違いとは?
有機栽培と慣行栽培の野菜の違いは大きく使用する肥料・農薬と育て方に関係しています。
おさらいですが、肥料は野菜によっての栄養、農薬は野菜によってくる害虫や病気を殺すための資材です。
有機栽培と慣行栽培では使っている肥料と農薬が大きく違う
有機野菜は農薬不使用・有機肥料のみ使用
有機肥料の特徴は、家畜の糞や、食品の残渣とかを利用した天然由来の農法であり、化学的な肥料は一切使用しません。
家庭で、料理した後に出てくる生ゴミや食品の残渣を加工すれば有機肥料になります。
他にも、海の海藻を自宅で干して粉々にしたもの、食べ終えたみかんの皮、余ったパンの耳など様々です。
そうなのですね!生ゴミも減ってちょっと楽^^笑
有機肥料は、市販のものももちろんあります。
<有機肥料の種類>
油粕: サラダ油やなたね油を絞ったときの残り粕
鶏ふん: 鶏のふんを加工したもの
魚粕: 魚の残渣
草木灰: 木や草を燃やした後の廃
骨粉: 鶏や豚の骨を燃やしたもの
米ぬか: 玄米を精選した後の残りもの
こういったものが一般的に市販で売られています。(もちろん、こちら以外にもたくさんあります。)
また、有機栽培では、基本的には農薬は使用していません。
どうしても、虫がついてしまうといった場合は、天然の成分を使って農薬を作り(油、石鹸水、唐辛子と焼酎を混ぜ合わせて発酵させたものなど)、まくこともまれにあるそうです。
※ただし、天然由来の農薬も使わないほうが野菜はよく育つので、要注意!使いすぎると、枯らしてしまうことも・・・
慣行栽培は農薬と化学肥料を使用
そもそも化学肥料とは?というところからの話ですが、こちらは、天然の鉱石(山や岩)などを削り、成分だけ抽出し、人工的に処理したものを肥料に使った農法です。
マメ知識ですが、化学肥料の元になっている天然の鉱石は、硝酸(しょうさん)という成分を含んでおり、こちらは、花火、ロケット、ダイナマイトなどを爆発させるための推進薬として使われることがあります。
え?ダイナマイトの使われている・・・??その成分を私たちは野菜を通じて摂取しているのですね・・・
「天然の鉱石」と聞くと何だか悪くなさそうなイメージですが、化学的な処理をすることで、硝酸という人間の体に有害な物質な出来上がるとのこと。
いかにも体に悪そうな感じで、嫌ですね〜><
化学肥料は、灰色のお米のような見た目です。

もともと、石や岩だったものを、散布しやすいようなかたちに化学的に処理したため、このような容姿になっています。
化学肥料には、硫酸カリ、硫安、過リン酸石灰やこれらを均等にまぜた配合肥料など、様々な種類があります。
また、慣行栽培のもう1つの特徴は、化学肥料に加えて、虫を殺す作用がある農薬も使用することができるとのことです。
日本では現在、99%の農家さんがこちらの農法を使用しています。
慣行栽培は、虫よけに農薬を使うとお伝えしましたが、そもそも、なぜ虫がつくのかわかりますか?
美味しいから?
現在、日本で出回っている野菜は、人間にとって食べやすいように、品種改良をされており、病害虫の抵抗性が低くなっています。
何百年前の野菜は今のような野菜でなく、ほとんど、雑草に近いようなもので、食べても苦く、下手したら、毒があるようなものでした。
それを、だんだん人間が食べやすいように改良していった結果、毒がなくなり、甘みと美味しさが特徴になりました。
現在の野菜は、人間も虫も美味しく感じるのです。
なるほど!では、原始人などは大変だったのですね><
なぜかというと、肥料をたくさんに散布することによって、人間にはわからないですが、虫にだけわかる匂いが野菜から出るようになります。
その匂いが出ると虫が寄ってくるのです。
へ〜!どんな匂いなんだろう?面白いですね^^
有機栽培の難しさと特徴は?
有機栽培に挑戦するにあたり、まずはその良さや難しさを事前に知っておくのが有効的です。
特徴① 有機野菜はゆっくり育つ
有機肥料は、土にまいたらすぐに野菜に栄養として吸収されるというわけではありません。
いったん、土の中にいる微生物が有機肥料を分解するという工程を経て初めて野菜そのものが吸収できるようになります。
なお、微生物が肥料を分解し、その後、野菜が吸収できるまでには時間が多くかかります。
特徴② 有機野菜は防御物質=栄養をたっぷり蓄えている
野菜に虫がつくという風景はよく畑で目にしますが、先ほど先生から説明があったように、野菜は、人間にはわからず、虫にはわかる特徴的な匂いを出しています。
この匂いに害虫が寄ってきて、野菜を食べようとしますが、有機栽培では、殺虫作用がある農薬が使えないため、野菜は農薬に頼らず、自分で自分の身を守らなくてはなりません。
そこで、害虫から身を守るために、虫にとって苦味があり嫌な物質である防御物質を出します。
こちらの防御物質は、健康食品や化粧品などにも使われていて、人間にとっては有益な栄養分であるビタミンCやポリフェノールを豊富に含んでいるのが特徴です。
野菜が自身で防御物質を貯める=人間にとっては栄養価が高い野菜が誕生するということです。

では、それに対して、慣行栽培で使用される農薬と化学肥料はどういった特徴があるのでしょうか?
まず、農薬についてですが、慣行栽培では、農薬の使用が許可されているので、野菜が自身で防御物質を出す前に手っ取り早く農薬を散布し、時間をかけずに虫や病気を殺します。
野菜は、人間が農薬を薬まいてくれるからいいか!と、自身で自身の身を守る体制を失います。
その際、有力な成分であるビタミンやプロフェノールなどの物質を作らなくなってしまう傾向があります。
結果的に、どんどん野菜の栄養価が低くなってしまいます。
また、もう1つの農薬の特徴としては、悪い害虫のみならず、害のない良い虫も同時に殺してしまうので、生態系や環境に影響が及ぼされます。
更に、慣行栽培は、有機栽培と反対に、野菜がすぐに成長するという特徴があります。
続いて、化学肥料の話になりますが、こちらの肥料は、化学微生物の分解が不要なものであり、水に溶けやすいのが性質としてあるため、土に水をかけたり、雨が降ったら、短時間で溶けて、野菜に吸収されます。
野菜は化学肥料から出た成分を栄養としてどんどん吸収していき、どか食いをしてしまうことで、メタボな状態になってしまいます。
また、化学肥料は水に溶けやすく、散布した量の半分以下は地下に流れます。
それが、ゆくゆくは川や湖に流れ、そこに住んでいる生き物(魚や微生物)に害を与えてしまうといった環境問題が生じます。
雨が多く降る時期なのでは、化学肥料の大半が下に流れてしまうため、流れた分を補うため、何度も繰り返し散布をします。
このサイクルを回していく中で、野菜は何度も栄養のどか食いをしてしまうことで太っていき、地下水はどんどん汚染されていくばかりといった悪循環が生まれます。
農薬のみならず、化学肥料を使用することで、野菜の味と栄養価が落ちるということも挙げられます。
<野菜の三大栄養素> 窒素、リン、カリ
窒素: 葉っぱを大きくする作用がある。
リン: 果実が実をつけるときに必要になる栄養素。
カリ: 根っこを育てるときに必要とされる栄養素。
この3つがあれば野菜は育つと言われています。
なお、実際には、三大栄養素だけではなく、カルシウム、マグネシウム、鉄、亜鉛など、人間の健康を維持するために必要ないろんなミネラルも含まれている。
しかし、化学肥料を使った野菜の場合、三大栄養素しか含んでいないことが多いのです。
逆に有機肥料を使った有機野菜は、こちらの三大栄養素にプラスしていろんな栄養素を含んでいます。
有機野菜は、豊富な栄養素があるため、味に深み(雑味)があり、食べたときに美味しく感じるのに対し、化学肥料を使った慣行栽培の野菜には三大栄養素しか入ってないため、味が薄く、単調になってしまうのが大きな特徴です。
講義の冒頭に、有機栽培と慣行栽培の小松菜の写真が登場しましたが、見た目や違ったのは、肥料の種類が影響していたことがわかりましたね!
特徴③ 有機野菜は硝酸(しょうさん)量が少ない
野菜の三大栄養素の中では、窒素が一番必要とされていますが、植物に吸収されるとき、窒素は硝酸というかたちで野菜に吸収されます。
硝酸は野菜の葉っぱに溜まりやすく、過剰に野菜が吸収してしまうと、葉っぱの色が濃くなり、えぐみが強くなります。
講義の初めに登場した小松菜で、2番の慣行栽培の小松菜は、硝酸をたくさん吸っていたので、色が濃かった、というのがその理由です。
では、そもそも硝酸とは何なのでしょうか?
強い酸性が特徴であり、金属を溶かしてしまうような物質であり、触ったり飲んだりすることもできない、危険なものです。
最初に少しお話した、火薬やロケットの推進薬に使われています。
なお、この状態は、人間が処理した状態であるため、本体の自然界では存在しないことを覚えておいてください。
野菜には、毒性が比較的に少ない硝酸塩(硝酸カリウムや硝酸カルシウム)が含まれています。
硝酸塩は他には、食品の防腐剤や添加物として使われています。
代表的な食材は、ハムですが、パッケージの裏ラベルを見ると、「亜硝酸」と記載がありますが、こちらはまさに硝酸から変化した物質です。
そんな硝酸は、現在、健康への危険性が世界中で叫ばれています。
硝酸の危険性:
過剰に摂取すると、アルツハイマー(認知症)、がん、チアノーゼ(血液が酸欠することで、顔や唇が青紫状態になり、ひどい場合は死に至る)などを発症することがあります。
また、硝酸は野菜そのものだけではなく、化学肥料が流れていった地下水から検出されることもあります。
有名な事件だと、1946年に、アメリカのアイオワ州の農園で酸欠状態になった赤ちゃんの事例が約2000報告され(そのうち7%は死亡)、その原因が、粉ミルクを溶かすときに使用された地下水から高い濃度の硝酸性窒素が発見されたことでした。(「ブルーベビー事件」)
有機野菜はどんなところがいい!まとめ
① 食味がいい
肥料をゆっくり吸収するため、えぐみがたまりにくく、濃厚な味に仕上がる。
② 環境への影響が少ない
化学農薬を使用しないため、肥料が地下に流れず、土や水が汚染されず、周りの生き物に影響しない。
③ 栄養価が高い
三大栄養素以外に数多くの栄養素を含んでいるため、食べたときに味が良いだけではなく、抗酸化作用があるなど、人間の健康維持に必要不可欠なミネラル、ビタミン、ポリフェノールを摂取することができる。
では、実際に、スーパーで販売されている野菜は危ないのか? この場で実験をします!
硝酸(野菜のえぐみ成分)を測る実験

では、スーパーの野菜にはどれくらいえぐみの成分が入っているのか?
有機野菜と比較してどうなのか?
について、硝酸メーターという機械で硝酸の量を図って比べたいと思います。
なかなか面白いですね!てか、硝酸メーターというものが市場に存在するのか。笑
実験の前に、資料に目を通します。
まずは、食品の基準が厳しい言われているEUで定められている硝酸の基準値を見てみます。

ほうれん草の事例を見ると、生のほうれん草1kgに対して3,500mgの硝酸の量が限度として設定されています。
3,500mgを超えた場合、人体への影響が危ないと見なされ、生産者さんも野菜を出荷できないという意味合いです。
硝酸が健康や環境に害をもたらすという事例が日本国内では調べられていないためです。
え〜!調べろよ〜!と思いますよね>< ヨーロッパに住みたい!笑
調査するのは、葉類代表のほうれん草(硝酸は、葉っぱの中に溜まりやすいという特徴があるため、葉類の野菜は特に高い値が観測される予測だとのこと)、果実代表のトマト、根っこ代表のにんじんです。
ん〜・・・どうだろう・・・EU基準を超えていないことを信じたい!という意気込みで記入してみました。

図り方は、先生が前もって絞ってくれた野菜の汁をスポイトで吸収し、数的をメーターの先っぽに入れるというやり方です。


まずはほうれん草。
結果は、な、な、なんと〜!4,200!!
EUが危険と定めている基準値を遥かに上回っているではないですか!
農家さんによっては、ほうれん草だと9,000mgを観測することも普通にあります。
そもそも日本では、硝酸の値は図られていないので、高い値が出ても問題なく出荷ができるということです。
げ〜!ほうれん草は健康に良いと思って、週2くらいでは食べているので、ショックです・・・
ちなみに、日本古来の野菜であり、おそらくほうれん草より頻繁に食べられている小松菜は一般的にもっと値が高いのだとか。
(理由は、硝酸は葉っぱだけではなく、軸にも溜まり、小松菜はほうれんそうより軸が長く太いためです。)
続いてトマトとにんじんですが、下記のような値が出ました。
・トマト:180mg
・にんじん:210mg

硝酸葉っぱに溜まりやすいため、葉物がダントツに多く含んでいます。
トマトの値が低いのは、果実の性質的に硝酸ではなく、別の成分(糖分など)を溜めやすい特徴があるためです。
また、にんじんは、根菜であり、根っこは肥料から野菜に吸収される硝酸の通り道であるため、葉物より少ないですが、果実系よりかはちょっと高い値が出ます。
ちなみに、以前私が自身で研究室で行なった実験では、にんじんは800〜1,000mgほどの結果となりましたので、同じ種類の野菜でも、やはり育てた人や畑などで異なることも覚えておいてください。
では、有機野菜の場合は、値が異なるのでしょうか?
先生が、事前に自身で測ってくれた有機ほうれん草(シェア畑で栽培されたもの)の値は・・・
1800〜2000mg!
一般野菜の半分!だいぶ違いますね!
しかし、mg単位で言われてもなかなかピンとこないな・・・
ということで、わかりやすく、今回用意されたほうれん草は1日でどれくらい食べることができるのか?を計算します。
今回の計算式の元は、WHO(世界保健機関)が出しているデータ:
体重1kgの人が1日で摂取できる硝酸は3.7mgまで
というのが参考なので、体重50kgと仮定すると1日の硝酸摂取量の上限は185mgとなります。
今回使った計算式はこちら↓

気になる結果は・・・
今回用意された慣行栽培のほうれん草は、1日1,7個ほどしか食べられないということがわかりました!
1,7個は、だいたいこれくらいです↓

通常、スーパーでは、1束で売っていおり、1束に含まれている個数は5~6個。
1パックまるごとは食べてはダメ!という結果になりました。
お鍋なんかに入れたら1束なんてぺろりなのに・・・硝酸について全く知らなかや自分が今までいかに硝酸を過剰摂取していたかを気づきました。
なお、有機のほうれん草である場合、硝酸の値は一般のものと比較して1/2ほどだったので、1日で食べられる個数でいうと、3〜4本くらいです。
更に、裏技としては、野菜は生ではなく茹でること。
湯がけば、硝酸の値は更に1/2へと減ります。(お湯に溶け出るのは、湯がいた後の水は使わないように!)
したがって、茹でれば、有機野菜のほうれん草だと、6本までは食べることができるということになります。

ちなみに、人間が健康的な生活を維持できるようには、1日350gの野菜が必要だ!と言われていますが、そんなに食べたら硝酸の過剰摂取になってしまい、逆に体に悪いのでは・・・?
その理由は、慣行栽培で育てられた野菜は栄養価が少ないためです。
一般野菜を350g食べても1日に必要な栄養値には達しません。
なお、有機野菜であれば、栄養価が何倍も高いので、350gより少なくても大丈夫です。
なお、硝酸というところでは、葉物はなるべく少なめにして、他の野菜を多めに摂るといいですよ。
なるほど〜!そう聞くと納得だし、有機野菜を食べたいと思いますね!
実験を通じて、自分の目で硝酸の値を確かめることができたのは本当に貴重な体験でした^^
なぜ日本人と外国人は有機野菜に対する関心・意識が違うのか?

ここで、講義の冒頭に、日本では有機栽培がなかなか広がらず、欧米では浸透が深いというところの理由を解説します。
理由① 日本の農協の規格が厳しい
農家さんは、野菜を作った後、農協に出します。
その農協には、段ボールの長さとおり、きっちり決められた個数の野菜を入れる必要があるなど、厳密な規格があり、例えば、少し曲がっていたり形が凸凹した野菜ができると農協に預けられなくなってしまいます。
例えば、きゅうりだと、長さ30cmでまっすぐなものを100本ダンボールに詰める必要性がありますが、曲がっているきゅうりができると、きっちり決められた本数が入らなくなってしまうなど。
しかし、真っ直ぐなきゅうりを作るのは難しいのです。
有機肥料だとゆっくりと栄養が吸収されるので、途中で形が曲がってしまうのが日常茶飯事。
それに対して、化学肥料を使用すれば、すぐに育ち、ピンとした真っ直ぐなきゅうりができやすくなります。
このように、流通の面を考えると、慣行栽培の野菜のほうが農協の基準に同格しやすいため、その点が日本で有機が普及しない1つの理由であります。
理由② 有機栽培は生産性や効率が悪いため、供給不足になる恐れがある
有機野菜は育てるのに時間がかかるため、生産効率が悪いのが特徴です。
日本では、国土の70%が山であり、国土全体で見ると畑の面積が少なく、生産性が落ちてしまうと、野菜の供給が需要に応えられなくなってしまう可能性があります。
理由③ 日本の消費者は見た目が良い野菜を求めてしまう
現在、農業で問題になっているのが消費者イメージの点。
虫にかじられた野菜や色が悪い野菜はなかなか買ってもらえないということがあります。
理由④ 海外では硝酸の研究が事例として報告されているため消費者意識が高く、栽培基準も厳しい
EUでは、硝酸の基準を超えた野菜は販売できないので、そちらに合わせて、やむをえず有機栽培にしないとならない背景があります。
また、農薬や化学肥料がもたらす身体への影響が研究結果として出ており、一般の人が危機意識が高いのも社会的な特徴です。
それに対して、日本は硝酸の基準値がないため、何を作ってもばれないというのが現状。
今後、日本で硝酸の基準値が導入される目処がたっていません。
なおもし厳しい基準値が設定された場合には、現在野菜作りをしている農家さんのほとんどが野菜を出せなくなってしまう恐れもあります。
理由⑤ 欧米では政府が有機農家を資金援助している
国にも寄りますが、ヨーロッパの一部の国では、有機農業へ転換した農家さんに政府から補助金が出ることがあるため、生産者さんにとってもメリットがあります。
*********************
確かに、これらのポイントを聞くと、日本と欧米では、政府の基準や消費者の意識が大幅に異なることがわかりますね!
自分の健康は自分で守る必要があるということで、有機野菜について正しい情報を知り、有機野菜を中心とした生活を送ることがいかに健康維持にとって大切であるのかを改めて実感しました。
有機栽培、自然栽培、無農薬栽培の違いは?
最後に、有機栽培以外で、現在ちょっとずつ普及してきている自然栽培と無農薬栽培について、その特徴や違いをご紹介します。
自然栽培とは?
栽培時、肥料を使わないのがその特徴です。
(ただし、飼った草、雑草、落ち葉などを土にまくのはOK。)
ただし、自然栽培の野菜は実はあまり美味しくありません。
例えを使うと、化学肥料がジャンクフード、有機肥料が健康的な食材、自然栽培は精進食でしょうか。(笑)
もちろん、慣れや好みにもよりますが、自然栽培の野菜はあじけない味になることが一般的です。
そうだったんだ〜!以前食べた自然栽培のじゃがいもは、確かにぱさぱさしていて味が薄かったということを思い出しました。
無農薬栽培とは?
農薬は一切使いませんが、肥料は使うことができます。
肥料は、有機肥料ではなく、化学肥料でも問題ないとされています。
よく、無農薬野菜のほうが有機野菜よいいいと間違った認識を持っている人がいますが、化学肥料が使用可能なので、必ずしもそうと言えません。
無農薬=有機栽培ではないということを覚えておいてくださいね!
有機栽培を詳しく学ぶための学校「アグリアカデミア」の紹介

シェア畑を運営している会社であるアグリメディアさんは、シェア畑のサービス以外にも、本格的に有機栽培を学ぶための学校「アグリアカデミア」を2017年に開講しました。
環境問題や食の安全に関して人々の意識が高まっている中、ここ数年間で、自分で野菜作りをしたいという方が増えており、その需要に応えるためだそうです。
講義の最後には、アグリアカデミアの講座への勧誘がありました。←ただし、ゴリ押しではなかったので、誤解がないように。(笑)
今世の中に出回っている有機栽培に特化した本や資料が少なく、シェア畑の8年間の研究・ノウハウを提供している学校です。
アグリアカデミアでは、有機野菜作りについて座学と実践が交互に行われており、開催は春・夏と秋・冬の年に2回、各講座の開催期間は半年です。
3〜8月のコースだとスケジュールはこんな感じ↓

半年間、毎週末畑または会議室での講義に通わなくてはならないので、かなり忙しい短期集中型のコースです。
シェア畑は現在、56農園ありますが、アグリアカデミアの開催場所は、神奈川と埼玉にある6農園のみと、現時点ではまだ限られているのが特徴。

シェア畑では詳しく触れないような、野菜作りの原理原則(なぜ?を考えることを大切に)、土作り(肥料選び、計算方法など)、栽培方法(あまり知られていない裏技など)、野菜の性質などを本格的に勉強するので、趣味の枠を超えた知識を取得でき、将来、農業を本業にしたい方にとってはかなり良い講座になっているかと思います。
また、有機栽培に関する知識だけではなく、将来就農をしたい方へのサポートや農業の人材派遣など、その他の幅広い援助を受けることができます。
このように、かなり本格的なコースでるとのことで、お値段も本格的(笑)。

うん、軽い気持ちでは始められませんね><
私は、現在シェア畑の会員であり、週1のペースで畑を耕していますが、有機野菜について、趣味レベルの範囲では、シェア畑で十分満足できる知識を得ていると感じたので、アグリアカデミアもちょっと気になったものの、結局入会を断念しました。
家庭菜園や自分で有機野菜を作ることに興味がある方は、まずシェア畑をやってみて、物足りないと感じたら、アグリアカデミアのコースに通ってみるというやり方もありかと思います。
まとめ

今まで私がもっていた有機野菜に関する知識は「なんとなく、体にいいから」というぼやっとしたものでありましたが、今回の有機野菜作りの講座を受けて、なぜ有機野菜が良いのかについて、本質的に学ぶことができたので、とてもためになりました。
有機栽培の野菜は、慣行栽培のものより何十倍も栄養価が高く、効率良く野菜から栄養を摂るための手段でもあります。
現在、一般スーパーで販売されている野菜の99%が一般野菜であり、なかなか全て有機野菜でまかなうということが難しいですが、引き続き、シェア畑で有機野菜を育てつつ、足りない部分は、有機野菜を宅配してくれる野菜宅配・通販サービスで補っていきたいと思います。
(有機野菜を多く取り扱っている野菜宅配サービスは、大地を守る会、坂ノ途中![]() 、ビオマルシェ
、ビオマルシェ![]() などです。利用をスタートする前、まずは料金がお得なお試しセットから注文することをおすすめします。)
などです。利用をスタートする前、まずは料金がお得なお試しセットから注文することをおすすめします。)
有機野菜生活にちょっとでも興味がある方は、同じく、是非シェア畑や野菜宅配の利用を検討してみてくださいね^^